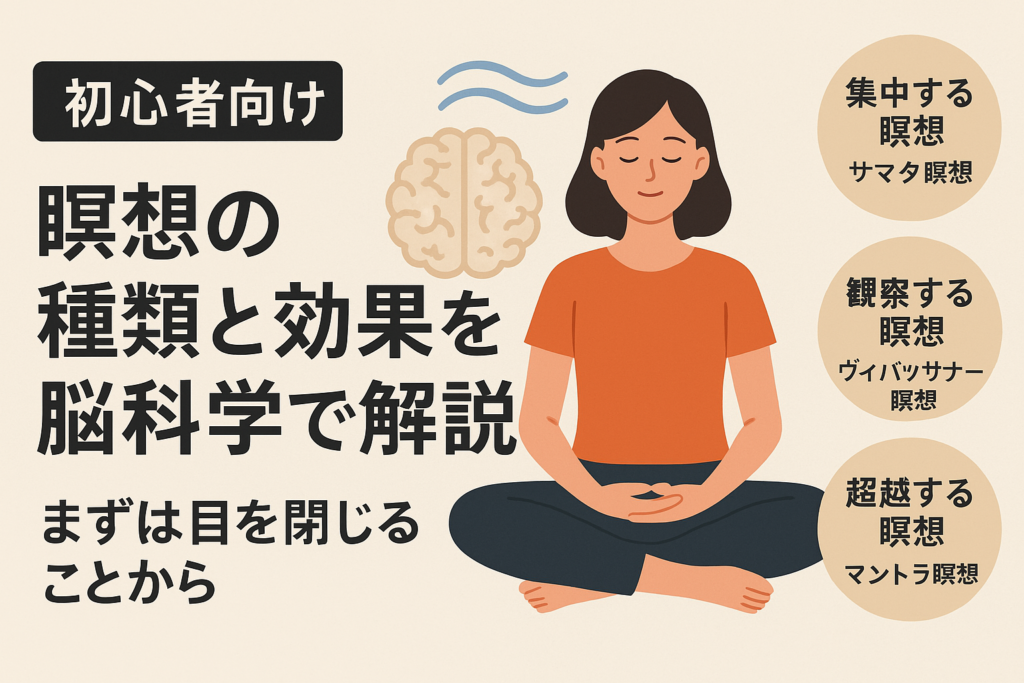
〜瞑想を脳科学からひも解く〜
忙しい毎日、常にスマホや人間関係、やることリストに囲まれていると、私たちの脳はずっと「オン」の状態。
まるで走りっぱなしのエンジンのように、思考も感情もノンストップです。
そんな脳を一度オフラインにして、リセットする時間――
それが「瞑想」です。
脳科学から見た瞑想の効果
瞑想は「ただ静かに座っている時間」ではありません。
実は、最新の脳科学では、瞑想をすると前頭前野(思考や判断をつかさどる部分)が活性化し、同時に扁桃体(不安やストレスに関わる部分)の活動が落ち着くことがわかっています。
つまり、瞑想を習慣にすると
・集中力が高まる
・ストレスへの耐性がつく
・感情に振り回されにくくなる
といった、現代人にこそ必要な“脳のメンテナンス”ができるのです。
瞑想には3つの種類があります
ひとくちに「瞑想」といっても、アプローチの仕方によって大きく3つに分けられます。
① 集中する瞑想(代表例:サマタ瞑想)
一点(呼吸やロウソクの炎など)に意識を集中させ、心の動きを鎮めていく瞑想です。
思考が散らかっているときや、集中力を高めたいときにおすすめ。
② 観察する瞑想(代表例:ヴィパッサナー瞑想)
浮かんでくる感情や身体感覚を「ただ観察する」瞑想。
「これは怒りだな」「今、腰が重いな」とラベリングしながら、感情に巻き込まれず距離を取る練習になります。
③ 超越する瞑想(代表例:マントラ瞑想)
マントラ(音や言葉)を繰り返すことで、思考を超えて深いリラックス状態へ入る瞑想。
寝る前や疲れをとりたいときにぴったりです。
まずは、目を閉じるところから
「瞑想」と聞くと、最初はハードルが高く感じるかもしれません。
7分間座るだけでも、長く感じる人も多いでしょう。
でも、大丈夫。
最初は1分でも、30秒でもOKです。
まずは目を閉じて、視覚からの情報をシャットダウンするだけでも、脳はホッとします。
静かに呼吸を感じる時間を、自分にプレゼントしてみてください。
まとめ
瞑想は、自分の内側に戻る時間。
脳にとっても、心にとっても、大切なリセットボタンです。
「何かをしなきゃ」と頑張りすぎてしまう人こそ、何もしない時間が必要です。
ぜひ、今日から1分でも「自分に戻る時間」、始めてみてくださいね。
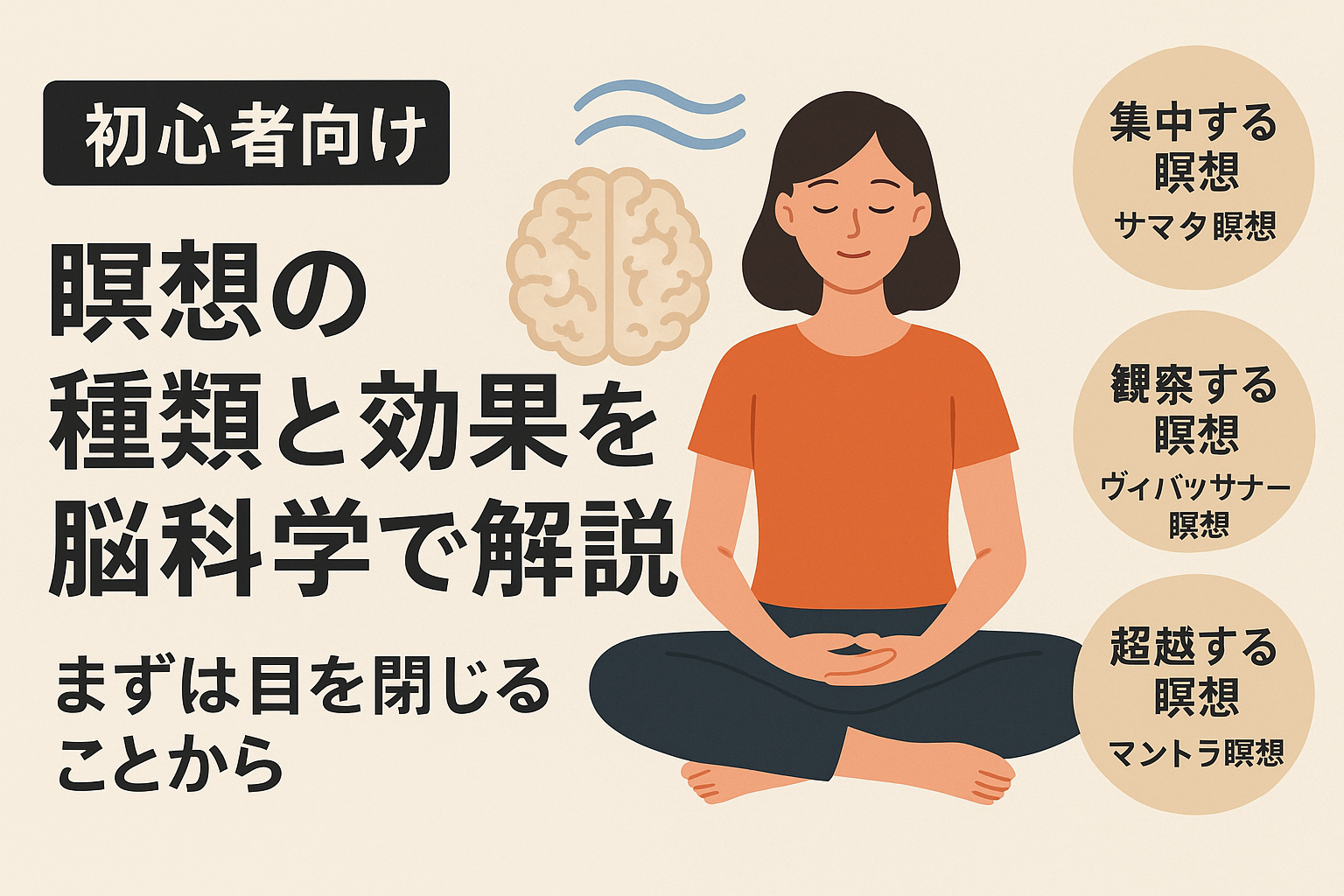
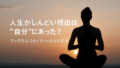
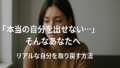
コメント